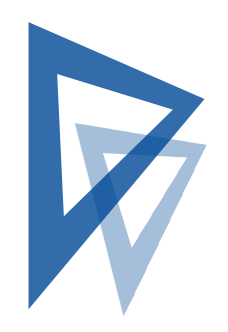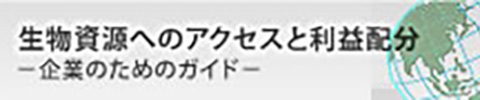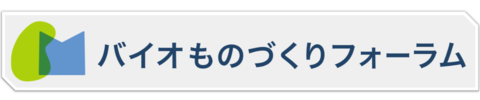Food Bio Plus研究会
「人と社会と地球」の健康を目指して、フードテックを活かした食料システムにおける社会課題の解決とグローバルを意識した産業の発展を支援するため、2022年12月に新たにFood Bio Plus研究会を立ち上げました。研究会では、「食」により「人と社会と地球」の健康を創造することを目指して活動します。国内外の食料システムが置かれた状況を把握し、消費者の加工食品選択の基準の変化を見据え、食料システムに関わる技術の実装化を支援し、持続可能な食料システムの構築と産業の発展を目指します。
幅広い技術を結集する「オールジャパンでの技術力」と新規開発食品の市場化に関わる「国内外でのルール形成力」、そして世界でも強い影響力を持つ日本の「食文化、美味創造力」を軸にして活動を展開いたします。活動内容につきましては、研究会会員の皆様と意見交換を行いながら、柔軟性と透明性を持って、具体化していく所存です。多くのJBA法人会員様にご入会いただきたくご案内申し上げます。
(入会資格:JBA法人会員 およびJBA個人会員(アカデミア))
会長・副会長

会長
小川 順 氏(京都大学大学院 教授)
副会長
竹内 昌治 氏(東京大学大学院 教授)
竹山 春子 氏(早稲田大学 教授)
石川 伸一 氏(宮城大学 教授)
飯島 明宏 氏(高崎経済大学 教授/Futurenaut(株)取締役 CTO)
清水 弘和 氏((株)ニップン 顧問)
設立発起人
阿部 啓子 氏(東京大学 名誉教授)
目的
バイオサイエンスに基づく産学官の共創による「食」の新たな価値の創造を通じて、日本の文化と強みを活かした産業を興し、「人と社会と地球」の健康に貢献することを目指して活動する。国内外の食料システムが置かれた状況と消費者の食品選択嗜好の変化を見据え、必要とされる技術やサービスの開発と社会実装を支援し、持続可能な食料システムの構築と産業のグローバルな発展を目指す。
活動内容
- セミナー開催等による情報(技術・海外・政策動向)の収集と共有
- 研究会内部での活発な議論をもとに、領域毎にワーキンググループを立ち上げ、各領域の課題に応じて以下の活動を推進する。
- ビジネスを推進するためのルール形成促進、規制緩和などに関する政策提言
- メンバー相互のオープンイノベーション
- 基盤構築に向けた国家プロジェクトの立ち上げの検討
- フードテックを普及させるための広報などの活動
今年度活動方針
日本の食文化や発酵(バイオ)技術の優れた強みを活かし、環境負荷の低減や日本の食料安全保障の解決の課題の解決に向けて、新規食品を主としたフードテックによる食料システムの変革を目指す。
発足3年目となり研究会員数も2倍となった2025年度も、「世界のフードテックの最新情報の提供」「特定課題に取り組むワーキンググループ活動」「企業同士のネットワーキングによる活性化(海外視察、GTB、マッチング)」「関連団体との連携した課題解決」という4つの柱の活動を引き続き活性化させる。研究会として関わる技術領域は幅広いが、「微生物利用による食料生産(プレシジョン発酵)」、「細胞性食品の開発推進」の社会実装に近い2領域を中心に「新規開発食品の社会受容性の向上」や「安全性評価制度等の法整備」などの課題解決に向け、本気でフードテックに取り組む会員企業や機関と共に、一層の加速・推進を目指す。
研究会メンバー
メンバー構成(2025年7月4日現在)
学界・ 公的研究機関等 32機関 / 産業界 104社 計136機関
本年度活動
- 研究会(年5回)、関連セミナーの開催
- 研究会会員限定セミナー動画配信 および 資料共有
- WG活動
- 各種団体等との意見交換、ヒヤリング(随時)
- Food Bio Plus 研究会 2025年度 第1回 研究会 セミナー「カーボンクレジットやバイオ炭による持続可能な農業の最前線」(2024年5月19日)
- Food Bio Plus 研究会 2025年度 第2回 研究会 セミナー「食品ロス対策への新しい取り組み」(2025年7月14日)
- Food Bio Plus 研究会セミナー「海外の昆虫利用産業の動向から考える日本の昆虫産業の今後の方向性」(2025年8月4日)
- Food Bio Plus 研究会シンポジウム(第77回日本生物工学会大会シンポジウム)伝統的発酵と革新的フードテックがもたらす食の新たな可能性」(2025年9月11日)
- Food Bio Plus 研究会セミナー「微生物が作り出すマイコプロテインの現在地~代替タンパク質社会実装に向けて~(2025年9月17日)
- Food Bio Plus 研究会 2025年度 第3回 研究会 セミナー「培養肉の実生産に向けたスケールアップへの取り組み」(2025年9月30日)
- BioJapan2025 主催者セミナー「日本のフードバイオの未来を問う ~世界を意識した新開発食品の安心安全構築~」(2025年10月8日予定)
- BioJapan2025 共同出展ブース JBA未来共創ブース:食×ヘルスケア×創薬×バイオエンジニアリング」および出展者プレゼンテーション「未来の食のイノベーション2025 〜実装と拡張への挑戦〜」(2025年10月8,9日予定)
- Food Bio Plus 研究会セミナー「日本が推し進める植物工場の現在地~社会実装と未来への可能性~」(2025年10~11月)
- シンガポール視察(2025年11月4~6日予定)
アグリフードテックエクスポ2025参加、企業訪問、サイト見学、試食、現地交流会、市場調査ほか(企画中) - 第4回研究会(2025年12月予定)
- Food Bio Plus 研究会セミナー「調理の未来:AI・ロボティクス・デジタルが創る新しい食体験」 (2026年1月企画中)
- 第5回研究会(2026年2~3月予定)
前年度活動
「人と社会と地球」の健康を目指して、フードテックを活かした食料システムの変革と新産業を創出するため、立ち上げたFood Bio Plus研究会も2年を迎え会員数も144機関と拡大。「新規開発食品の受容性」、「微生物による食料生産(精密発酵)」、「培養肉の開発促進」、「昆虫利用した未利用資源の活用」という領域で、2024年度はセミナーを12回実施し、今年は海外(イスラエル、シンガポール)スタートアップも含め最新情報を積極的に発信。セミナー登壇からの研究会入会およびネットワーキングを促進し共創の場を提供。精密発酵ワーキンググループ(WG)では共通の課題と解決策を議論し、当WGから来期申請に向けた社会実装活動を積極的に推進。消費者庁および農振水産省へ通い、新開発食品に関する意見交換を実施。また、消費者庁新開発食品調査部会に参加し培養肉における安全性評価制度等の法整備について提言。関係省庁・団体へ働きがけし、フードテックを新産業として創り出し、社会実装の実現を目指す活動を行った。
入会方法・お問い合わせ
*JBA非会員の方でご興味をお持ちになられた方はこちらまでお問い合わせください。
お問い合わせ
(一財)バイオインダストリー協会
Food Bio Plus 研究会 事務局
(担当:大木、安田、坂元、矢田)
E-mail:fbp2022(at)jba.or.jp ((at)を@に変えてください)