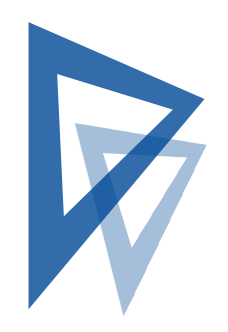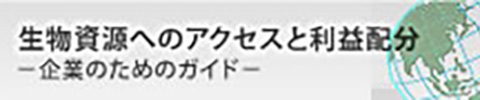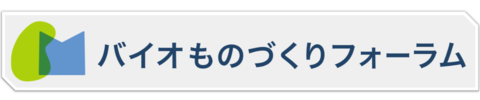新資源生物変換研究会
新資源生物変換研究会は、1988年に石油発酵研究会とC1微生物日本国内委員会が合併、発足しました。以降、炭化水素、C1化合物、化学工業製品、バイオマス等、各種の新しい資源の生物変換および環境調和・改善技術に関する基礎・応用・開発研究を促進してきました。微生物を中心とした生物による物質変換・ものづくり等に関連する分野を広く対象とし、学界、産業界、公的研究機関の専門家が幹事・名誉会員となっています。

会長 阪井 康能
(京都大学 名誉教授)
会長・副会長
会長
阪井 康能 氏(京都大学 名誉教授)
副会長
乾 将行 氏((公財)地球環境産業技術研究機構 バイオ研究グループ グループリーダー 主席研究員)
松山 彰収 氏((株)ダイセル ヘルスケアSBU 事業推進室 事業戦略G)
目的
炭化水素、C1化合物、化学工業製品、バイオマスなど各種の新しい 資源の生物変換及び環境調和・改善技術に関する基礎及び応用研究の促進
活動内容
講演会の企画
日本生物工学会、日本農芸化学会で開催するシンポジウムを企画し、学会と共催でシンポジウムを開催しています。
BioJapanセミナーの企画
環境・エネルギー、ものづくり分野に関するシンポジウム、展示等の企画に協力しています。
研究会メンバー
メンバー構成
学界 30名 / 産業界 43名 / 公的研究機関等 12名 計85名(2025年4月1日現在)
前年度活動
- 2025年3月7日
日本農芸化学会2025年度大会シンポジウム「新資源を考える ~バイオマス・廃棄物・CO2・C1・水素~」
資源作物ソルガムにおけるネガティブエミッションとグリーンケミカル製造 田丸 浩(東北大グリーンクロステック、東北大院工)
タイ非可食資源と膜を用いた非可食糖製造プロセス 栗原 宏征(東レ(株))
嫌気性酢酸生成菌による多様な資源からのバイオものづくりの可能性 中島田 豊(広島大院統合生命)
水素社会におけるCO2 資源化 ~水素細菌の代謝特性と活用~ 亀谷 将史,新井 博之(東大院農、東大微生物連携機構)
" C1 ケムバイオエコノミー"持続的なバイオものづくりと温室効果ガス削減を目指して~ 阪井 康能、由里本 博也(京大院農)
バイオものづくりにおけるこれからの主原料 原 吉彦(味の素(株))
- 2025年1月7日
第5回勉強会「オートファジー研究と応用の最前線」
健康長寿実現の鍵を握る細胞機能・オートファジー 吉森 保(大阪大学 名誉教授)、石堂 美和子((株)AutoPhagyGo取締役社長)
オートファジーによるタンパク質品質管理:相分離p62とそのオートファジー分解 小松 雅明(順天堂大医学部教授)
複合微生物系によるオートファジーを活性化する腸内代謝物の生産 中島 賢則((株)ダイセル 事業創出本部バイオデザインチームチームリーダー)
- 2024年9月9日
第76回日本生物工学会大会シンポジウム 「高付加価値物質生産"セルファクトリー"の設計戦略」
イソプレノイド高生産菌「進化(DBTL)」の進化 梅野 太輔 (早大・先進理工)
植物におけるポリイソプレノイド合成・蓄積機構に基づくポリマーファクトリーセルのデザイン 高橋 征司 (東北大院・工)
シグナル分子を介した二次代謝生合成制御システムの理解と合理的制御による物質生産戦略 荒川 賢治 (広島大院・統合生命科学)
嫌気性の化学合成独立栄養微生物を使ったセルファクトリーに必要なユーティリティ設備設計 加藤 淳也 (産業技術総合研究所)
- 2024年5月20日
第4回勉強会「バイオイノベーションの最前線:高効率蛋白質改良とナノドロップレットスクリーニング」
機械学習が導くタンパク質の加速進化 梅津 光央 (東北大学 大学院工学研究科 教授)
ミリオンスクリーニングの今とこれから 小笠原 渉 (長岡技術科学大学 技学研究院 技術科学イノベーション系 教授)
入会方法・お問い合わせ
本研究会の運営・企画等への積極的な参画にご興味があるJBA法人会員・個人会員(ただしアカデミア所属の方のみ)の方がいらっしゃいましたら、下記事務局までメールでお問い合わせください。
お問い合わせ
(一財)バイオインダストリー協会
新資源生物変換研究会事務局 村尾・本田・清水
TEL:03-6665-7950 E-mail:greenbio(at)jba.or.jp ((at)は@に置き換えて下さい)