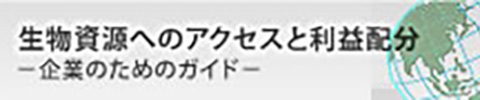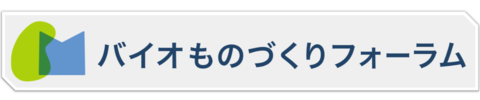バイオエンジニアリング研究会/ テクニカルセミナー8「生物資源×データ技術:新たな価値創出への挑戦」
開催概要
【開催日時】 2025年 8月1日(金)14時~16時45分
【会場】 JBAオフィス先着20名および MS-Teams によるオンライン開催 定員500名
【会場URL】 https://www.jba.or.jp/images/JBAmap1_new.jpg
【定員】 20人
【主催】 (一財)バイオインダストリー協会 バイオエンジニアリング研究会
【協賛】 (公社)日本生物工学会(予定)
近年、未利用の植物資源や遺伝資源に注目が集まり、それらをデータ技術と 融合させることで、新たな産業の可能性が広がっている。多角的な視点から、資源の潜在力を最大限に引き出し、新たな価値を創造するための取り組みについて議論を深め、幅広い分野の皆様にとって、最新の知見とネットワーキングの機会を提供する場となることを目指す。
「若手ダイナモ人財小委員会」・「バイオエンジニアリングにおけるオミックス解析技術」
「バイオ製品開発のDX・自動化」小委員会企画協力
座長:養王田 正文 氏(東京農工大学大学院 工学研究院 教授 バイオエンジニアリング研究会 副会長)
Coordinator:松田 朋子 氏((株) 日本バイオデータ Senior Principal Scientist
大阪大学大学院 工学研究科生物工学専攻 招へい 研究員
バイオエンジニアリング領域若手ダイナモ人財小委員会副リーダー)
プログラム
14:00~14:05
はじめに
養王田 正文 氏(東京農工大学大学院 工学研究院 教授、バイオエンジニアリング研究会 副会長)
14:05~14:40
特 別 講 演:食感分析・設計・製造実現に向けた課題と 解決への模索
~食感AI分析とフード3Dプリンタによる新規食感創出法開発~
武政 誠 氏(東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 物質生命理工学専攻 教授)
食感は分析も設計も困難で、官能評価や経験則に基づいて実施されており課題が多い。この困難は、「食感が高分子濃厚系における高分子間相互作用に起因」し、特に大変形においては非線形性が強い点、に起因し、多成分かつ不均一系ではさらに困難となるため、短期的に理論など正攻法によって解決されそうな見込みは薄い。我々はこの複雑系に対して、(1)「食感AI分析」開発で取り組んでいる。10万回規模で食感ビッグデータ取得したシステム3種を活用したディープラーニングに基づいた食感解析法で、既存手法を凌駕するポテンシャルを示した事例に触れ、また(2) 3Dプリンタ開発により食品の内部構造を設計およびプリント(製造)し、既存食品の食感模倣や新規食感創出に取り組んだ事例、を中心に紹介する。
14:40~15:15
未利用の海外植物遺伝資源を 使った新たな商品の 研究・開発への挑戦
矢野 貴裕 氏、楠奥 比呂志 氏(平田機工(株) 研究開発本部 遺伝資源研究開発部)
世界各地に眠る未利用の植物遺伝資源を活用し、機能性食品や化粧品、トイレタリー、医薬品の開発を目指す「ぷらんつプロ」の取り組みを紹介。未利用植物情報の開拓や伝統的知識の活用を通じた新規ビジネスの可能性について議論。
15:15~15:50
ヤンマー×酒造メーカー×米生産者で、 "三方良し"を目指した新しい 酒米プロジェクト
新井 由紀 氏(ヤンマーホールディングス(株) 技術本部 中央研究所 バイオイノベーションセンター)
ヤンマー、酒造メーカー、米生産者、そして名古屋大学の共同研究により、新たな酒米の開発を目指したプロジェクトを実施した。
同プロジェクトの背景、経緯、成果を中心に、同社の育種技術によるサステイナブルな取組みについて解説いただく。
15:50~16:25
生物資源とデータ技術の融合:シャノンとラマルクから考えるデータと生物の未来
緒方 法親 氏((株)日本バイオデータ 代表取締役 大阪大学大学院 工学研究科 生物工学専攻 招へい教授)
生物資源とデータ技術を融合させるとき、重量や長さの測定はどれほどの喪失を伴うか。喪失を減じ、不正を緩和する技術はどれで、その正当性はどのように論証しうるのか。これに答えられるなら、生物種を問わず、目的すら問わない、目視と同様に前提とすべきデータ技術がつくれるのではないか。我々の作ってみたものを紹介し、可能であれば質疑応答によってこれを検討する。
16:25~16:40
総合討論(15分)
座長:養王田 正文 氏(東京農工大学大学院 工学研究院 教授、バイオエンジニアリング研究会 副会長)
16:40~16:45
おわりに
Coordinator:松田 朋子 氏((株) 日本バイオデータ Senior Principal Scientist
大阪大学大学院 工学研究科生物工学専攻 招へい 研究員
バイオエンジニアリング領域若手ダイナモ人財小委員会副リーダー)
※講演プログラム・講師について ⇒ こちら をご参照下さい。(PDF 593KB)
参加方法
講演会参加費
無料
お申し込み
マイページにログイン後、最下部の申込ボタンからお申込み下さい。
※セミナーのお申し込みには、会員・非会員問わず、マイページのご登録申請が必要となっております。マイページ未登録の方は、こちら よりご登録をお願いいたします。
マイページの申請から登録完了までには数日お時間をいただく場合がございます。お早めにマイページ登録をお申し込みください。
※こちら からもお申込み可能です。
お申し込み締め切り
7月30日(水)
※参加登録完了後に申込完了メール、前日にリマインドメールを送信いたします。
※セミナーURLは申込完了メールとリマインドメールメールに添付いたします。
※メールが届かない場合は、下記担当者にご連絡下さい。
お問い合わせ
(一財)バイオインダストリー協会(担当:橋本、矢田)
E-mail:hashimotosnj(at)jba.or.jp ((at)を@に変えてください)
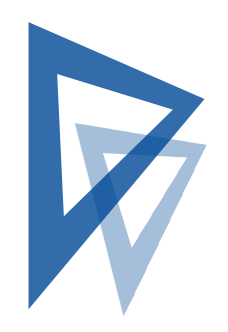 Recommended Links
Recommended Links